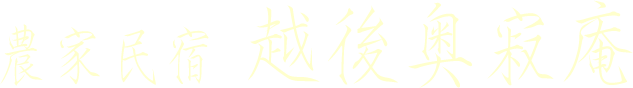この文章は鈴木大拙のご著書「日本的霊性(岩波新書)」からの引用です。
天日は有難いに相違ない。またこれなくては生命はない。生命はみな天をさしている。が、根はどうしても大地におろさねばならぬ。大地に係わりのない生命は、本当の意味で生きていない。天は畏るべきだが、大地は親しむべく愛すべきである。大地はいくら踏んでも叩いても怒らぬ。生まれるも大地からだ。死ねば固よりそこに帰る。天はどうしても仰がねばならぬ。自分を引取ってはくれぬ。天は遠い、地は近い。大地はどうしても母である、愛の大地である。これほど具体的なものはない。宗教は実にこの具体的なものからでないと発生しない。霊性の奥の院は、実に大地の座に在る。平安人は自然の美しさと哀れさを感じたが、大地に対しての努力・親しみ・安心を知らなかった。従って大地の限りなき愛、その包容性、何事も許してくれる母性に触れ得なかった。天日は死した屍を腐らす、醜きもの穢らわしいものにする。が、大地はそんなものを悉く受け入れて何等の不平も言わぬ。かえってそれらを綺麗なものにして、新しき生命の息を吹きかえらしめる。平安人は美しき女を愛して抱き留めたが、死んだ子をも抱きとる慈母を忘れた。彼らの文化のどこにも宗教の見えないのは、固より然るべき次第である。
人間は大地において自然と人間との交錯を経験する。人間はその力を大地に加えて農産物の収穫に努める。大地は人間の力に応じてこれを助ける。人間の力に誠がなければ大地は協力せぬ。誠が深ければ深いだけ、大地はこれを助ける。人間は大地の助けのいかんによりて自分の誠を計ることができる。大地は詐らぬ、欺かぬ、またごまかされぬ。人間の心を正直に映しかえす鏡の人面を照らすが如くである。大地はまた急がぬ。春の次でなければ夏の来ぬことを知っている。蒔いた種子は、その時節が来ないと芽を出さぬ、葉を出さぬ、枝を張らぬ、花を咲かせぬ、従って実を結ばぬ。秩序を乱すことは大地のせぬところである。それで人間は、そこから物に序あることを学ぶ、辛抱すべきことを教えられる。大地は、人間にとりて大教育者である、大訓練師である。人間は、これによりてみずからの完成をどれほど遂げたことであろうぞ。
それから人間は、大地によるが故に天日の恩を知ることができる。天照らす天日の力を、大地なくては感ぜられぬ。大地は人間の呼びかけに直接に応えるが、天日は遠くして手が届かぬ。祈りは捧げられるが、それ以上は人間の力は及ばぬ。人間は、天に対しては絶対に受動的である。天は畏るべきほどに、愛せられぬ。人間は、天に対して懾服を知るのみである。もし天の愛に親しみ得られることがあるとすれば、それは大地を通してである。天との直接の交渉では、天意の行動をそのままに受入れるよりほかない。日は焼きつく、木の蔭のない限りは焼けるままである。風が吹き雨が降る、これを凌ぐは巌の下の洞窟よりほかない。いずれも大地の助けによらねばならぬ。それから春の暖かさは、大地に萌ゆる草花によりて親しく感ぜられる。単にこの身の気持がよいだけでは、天日の有難さは普遍性をもち得ぬ。大地と共にその恵みを受ける時に、天日はこの身、この一個の人間の外に出て、その愛の平等性を肯定する。本当の愛は、個人的なるものの奥に、我も人もというところがなくてはいけない。ここに宗教がある、霊性の生活がある。天日だけでは宗教意識は呼びさまされぬ、大地を通さねばならぬ。大地を通すというのは、大地と人間と感応道交の在るところを通すとの義である。中空にぶらりとさがっていては、天日の恵も何もわからぬ。足が大地に着いていて、そしてその大地はまた、自分の手をなんとかして又いくらか加え得るものであるが故に、それを通して天日が感ぜられる。天の行動はかくして、大地によりて人間と交渉してくる。天に対する宗教意識は、ただ天だけでは生まれてこない。天が大地におりて来るとき、人間はその手に触れることができる。天の暖かさを人間が知るのは、事実その手に触れてからである。大地の耕される可能性は、天の光が地に落ちて来るということがあるからである。それゆえ宗教は、親しく大地の上に起臥する人間 ー 即ち農民の仲から出るときに、最も真実性をもつ。大宮人は大地を知らぬ、知り能わぬ。彼らの大地は観念である、歌の上、物語の上でのみ触れられる影法師である。それゆえ平安の情緒は宗教とかなりに隔たりのあるものである。仏教者という人々のあいだでも、宗教は出世の媒介にこそなれ、自分の心の奥へ分け入る枝折にはならなかった。南都北嶺の仏教、いずれも人間的真実性を欠いている、直接に大地に触れていないからである。四百年の冬眠はずいぶん長いが、歴史的・政治的・地理的諸条件は、それを余儀なくせしめた。しかしこの眠りは無駄ではなかった。
平安時代は、一方では大宮人をして恋のあわれの優しいの床しいのという観念世界に、寝たり起きたりすることを許していたが、また他の一方 ー 即ち地方では、農民と武士をして大地と最も直截な交渉を続け得ることをした。後者はそれ故に生命に直面していたのである。平安の大宮人に、政治的にも思想的にも取って替るべきものは、農民をじかに支配していた階級、即ち武士でなくてはならなかったのである。生命の真実を把握しているもののみ、集団生活の指導者となることが許される。中央に志を得なかった者が地方に行ったというが、その頃の志というのは、大臣になったり、納言になったりすることであった。それで少しく気概のある大和男児 ー その頃も多少はあったに相違ないが、それらはそんな下らぬことに思いを煩わすまでもなく、みずから進んで行けるなら外国までへも出て、その雄図の実現につとめたであろう。優さ男の真似をしたり、歌よむ女の部屋の戸を水鶏のように叩くなどいう時代の趣味のみを逐うことに汲々たらんは、丈夫のすべきことではない。もっと真実の生活をしたいと、彼らは願ったに相違ない。即ち大地に近い生活 ー たとい無意識であっても ー を、やって見たいと思ったのであろう。平安時代の後期には、こんな有為の人物が、地方で潜行的に、有形無形の勢力を積み上げた。中央政府の権威はいつかは失墜するに極っているのだから、大地に足ふみしめているものが、あらゆる意味でそれに取って替るべきであるのだ。
以上の所述は霊性生活において、ことにその然るを見るのである。霊性と言うといかにも観念的な影の薄い化物のようなものに考えられるかも知れぬが、これほど大地に深く根をおろしているものはない、霊性は生命だからである。大地の底には、底知れぬものがある。空翔けるもの、天降るものにも不思議はある。しかしそれはどうしても外からのもので、自分の生命の内からのものではない。大地と自分とは一つのものである。大地の底は、自分の存在の底である。大地は自分である。都の貴族たち、そのあとにぶら下がる僧侶たちは、大地と没交渉の生活を送りつづけた。彼らの風雅も学問も、幽玄も優美も空中の楼閣で、本当の生命、真実の生活とかけ離れたものであった。平安時代を通じて一人の霊的存在・宗教的人格と見るべき人の出てこなかったのは、当に然るべきところである。弘法大師の如き、伝教大師の如きといえども、なお大地との接触が十分でない。彼らの知性・道徳・功業は実に日本民族の誇りである。が、彼らは貴族文化の産物である。それで貴族文化のもち得べき調書と短所とを悉く備えている。彼らは、平安文化の初期に出世したので、平安文化の特徴と見るべき繊弱さ・哀れさ・麗わしさ・細やかさなどいう情緒を持ち合わさぬ、大陸的なところがある。しかし彼らの仏教は、南都の仏教に対して一時は清新な溌剌なものであったが、時を経るに従い、他の文化形式と同じく形式化・儀礼化・審美化・技巧化の一路をたどって、仏教本来の意味から離れるようになった。大陸からの刺激を受けず、島国に閉じ籠り、京都の山々に囲まれ、地方からの経済的支援で生活した貴族たちは、風雅な遊びで一生を暮すほか、権力筋へ何かで渡りをつけて「栄位」につくことを、「一門の誇り」としてものであった。その跡を逐う僧侶たちは、出世間の人として彼らを導くことの代りに、彼らにひきずられていった。
平安文化を描写する人は、当時の男が女の真似して、服装美や容色美に苦心したことを記している。「男性の服飾」がいかに色彩美の豊かなものであったかは、当時の「物語」を読むものの誰しも気づくことである。袴などは男女が取替えて着ても差支えないほどであった。のみならず衣裳には薫物の香のめでたく床しいのを炷きしめ、顔は脂粉で飾ることを怠らなかった。それから彼らはまた不思議に涙脆かった。何かというと、「袖も絞るばかり」「涙に濡れる」のである。「河原のいとあらましきに、木の葉の散りかふ音、水のひびきなど、哀れもすぎて物恐ろしく、心細きところなり」というほど無闇に感傷的であった。
僧侶の身なりも各種の儀式もまた従って貴族趣味や女性的情緒を基調とせざるを得なかった。法会に集まる念仏誦経の坊さんたちは、「いみじう美しう、をかしげなること限り」なかった。そしてその服装は、「或は紫の織物の指貫どもを、濃き紫に薄紫にて、たけに二尺ばかり踏みしだき、…薄鈍の袿、糊張などの綾、無文あるは固文の織物、また今様のつやつやなどいふをぞ、六つ許りづつ綿薄らかにて着せたる。云々」というので、なかなか形容しきれないのである。それから「香のかうばしきこと限りなし、衣に惹かれてありき舞ふほど、いとよだけげなり」で、臭覚の世界も唯ならぬ光景である。「頭には花をぬり、顔には紅・白い物をつけたらんやうなり」、「声どものひ若く細く美しげにきかまほしきこと、迦陵頻伽の声もかくやときこえ」たと書いてあるから、宗教的行事の様態もすべて感覚的なものであったことがわかる。
こんな生活も意味のないことはないが、これに乗じてのみいては、足もとが危うくなるよりほかない。平安文化はどうしても大地からの文化に置き換えられねばならなかった。その大地を代表したものは、地方に地盤をもつ、直接農民と交渉していた武士である。それゆえ大宮人は、どうしても武家の門前に屈伏すべきであった。武家に武力という物理的・勢力的なものがあったためでない。彼らの脚跟が、深く地中に食い込んでいたからである。歴史家は、これを経済力と物質力(または腕力)と言うかも知れぬ。しかし自分は、大地の霊と言う。
大地の霊とは、霊の生命ということである。この生命は、必ず個体を根拠として生成する。個体は大地の連続である、大地に根をもって、大地から出で、また大地に還る。個体の奥には、大地の霊が呼吸している。それゆえ個体にはいつも真実が宿っている。観念の世界に対して一極を分有すると言ってよい。平安朝の仏教は、観念の極に立っていた。それで貴族文化に追随して、遊戯気分を離れ得なかった。『古今集』に、
世の中は夢かうつつかうつつともゆめとも知らずありてなければ
という歌があるが、こんなことで済ましていては、宗教の世界は見えるものではない、霊性の消息はうかがわれるものではない。「憂し」とか、「寂し」とか、「世を厭う」などいうと、もう仏教がそこにあるように考える人もあろうが、平安時代には、とにかく大地から芽生えたものはなかった。武家が公卿に代ったというは、腕力が観念に代ったという意味にとられてならぬということは、さきにちょっと記した。武家は腕力をもってはいたが、武家の強さはそれではない。武家の強さは、大地に根をもっていたというところにある。武家はいつも大地を根城としていたのではない。武家は腕力はある、武家と腕力とは離れられぬ。が、大地に根ざさぬ限り、腕力は破壊する一方だ。公卿文化は、繊細性の故に亡びる。武家文化は、その暴力性・専横性などの故に亡びる。腕力と大地とは一つものではない。腕力だけしかないものもある。公卿たちでも大地が顧みられていたら、平安時代のようなことはあるまい。この点を深く考えなければならぬ。平安時代に取って代った鎌倉武士には、力もあり、またそのうえに霊の生命もあった。力だけであったら、鎌倉時代の文化は成立しなかったであろう。鎌倉文化に生命の霊が宿っていたということは、その宗教方面にも見られる。
平安時代は、あまりに人間的であった。鎌倉時代は、霊の自然・大地の自然が、日本人をしてその本来のものに還らしめたと言ってよい。