縁・間・離・奥にひらかれる感覚
日本の家屋は、
ただ暮らしを便利にするための器として
つくられてきたのではありません。
そこには、
人がどのように内面と向き合い、
どのように世界と関わるのかという、
霊的な秩序が、静かに織り込まれてきました。
家の外から内へと足を進めるとき、
私たちは無意識のうちに、
縁をくぐり、間を通り、
次第に奥へと導かれていきます。
その先、最も奥まった場所には、
床の間が設えられてきました。
そこは、装飾のための空間ではなく、
掛け軸や花を通して、
目に見えないものと向き合うための座です。
この動線は、
地面に近い場所から、
少しずつ高さを増しながら、
俗から離れ、内奥へと向かう構造を持っています。
日本の空間は、
移動することそのものが、
内なる静けさへと近づいていく旅となるよう、
設えられてきたのです。
日本家屋の構造としては、
奥のさらに先に「離れ」が設えられてきました。
しかし、意識の深まりにおいては、
まず俗から離れることで、
はじめて奥がひらかれることもあります。
縁
河合隼雄は、
日本人は「自我」よりも、
より深いところにある「自己」との親和性が
高いと述べています。
それは、
自己を明確な輪郭で囲い、
他者や世界と線を引くというよりも、
関係性のなかで自らを感じ取っていく在り方です。
実際、地方の暮らしに目を向けると、
先祖代々受け継いできた土地は大切にされる一方で、
隣家との境界は、
驚くほど曖昧なまま保たれてきました。
線を引くことよりも、
共に在ることが優先されていたのです。
日本の家屋には、
その感覚が空間として表れています。
暖簾や縁側は、
外と内を分けるための装置ではなく、
両者が出会い、交わるための場でした。
部屋と部屋のあいだも、
壁ではなく、
襖や障子によって仕切られてきました。
そこでは、
完全に隔てることも、
完全に開くこともなく、
気配が行き交います。
もともと日本人には、
西洋的な意味での強固な自我境界は、
必ずしも必要ではなかったのかもしれません。
境界を守ることよりも、
縁を結び、縁を育てること。
その価値観は、
暮らしの作法として、
そして建築のかたちとして、
静かに受け継がれてきました。
日本の空間に身を置くとき、
私たちは知らず知らずのうちに、
「分ける」ことよりも、
つながりのなかに在る自己へと、
立ち返っていくのです。
間
河合隼雄は、
日本の神話や物語の構造に、
一見すると役に立たない存在、
意味を持たないかのような神々が
要の位置に置かれていることに注目しました。
それらは欠落でも未完成でもなく、
意味が固定されない中空の場として、
物語全体を生かしている。
河合はそこに、
日本文化特有の「中空構造」を見ています。
日本の空間にも、
同じ感覚が流れています。
家屋には、
物を過不足なく配置するというより、
あえて置かない場所が残されてきました。
とりわけ、
祭事や客を迎えるハレの間では、
家具や調度は最小限に抑えられ、
空間そのものが主役となります。
何もないからこそ、
人の振る舞い、気配、沈黙が
そこに立ち上がるのです。
中庭や土間、
部屋と部屋のあいだに生まれる余白も、
通過のためだけの場所ではありません。
そこには、
立ち止まり、遊び、
ときに目的を失うことが許される
遊びの間がありました。
日本の「間」は、
何かを欠いた空白ではなく、
次の動きや意味が
自然に芽生えるための余地です。
詰め込まず、決めすぎず、
ただ開いておく。
その余白があるからこそ、
空間も、人の心も、
息をし続けることができるのかもしれません。
離
人工的につくられ、
効率や成果が優先される都市の空間では、
人は知らず知らずのうちに、
他者との比較や競争のなかで
自らを測るようになります。
自意識が強まり、
自我の輪郭は硬くなり、
「どう生き残るか」という問いが、
思考の中心を占めていきます。
しかし、
世俗から一歩距離を置き、
自然に囲まれた里山に身を置くと、
その感覚は少しずつ変わり始めます。
山の稜線、
風の音、
雪に覆われた静けさ。
それらに包まれているうちに、
自我を守るために張り巡らせていた境界は、
次第に緩んでいきます。
自然と人、
自己と他者を隔てていた線だけでなく、
意識と無意識のあいだにあった境界も、
また、柔らかくほどけていきます。
すると、
論理や計画の外側から、
イメージや物語、
神話的な感覚が立ち上がってきます。
それは空想ではなく、
世界と深く触れ合ったときに
自然に生まれてくる語りです。
ここでは、
他人より秀でることが目的ではなくなります。
自然に生かされているという事実が、
理念としてではなく、
身体の感覚として受け取られるように
なるからです。
都市では、
生き延びるための戦略が
思考を導いていました。
けれども自然のなかでは、
戦略よりも先に、
自分の本質を味わうことが
何よりも大切な営みとなっていきます。
俗から離れるとは、
どこか特別な場所へ
逃れることではありません。
重ね着してきた役割や思い込みを脱ぎ、
本来の感覚に還っていくための、
静かな転回なのです。
奥
奥には、
何か特別なものが
置かれているわけではありません。
そこにあるのは、
ただの空。
何もない場です。
日本の空間において、
最も大切なものは、
常に目立たないところに置かれてきました。
西洋の街では、
教会が中心に据えられ、
どこからでも見上げることのできる
父性的な神の象徴として、
高くそびえ立ちます。
一方、日本では、
集落の中心ではなく、
その外れに、
さらに森の奥へと分け入ったところに、
ひっそりと社が祀られてきました。
そこでは、
神聖なものは姿を現しません。
像もなく、
語りもなく、
ただ、空があるだけです。
日本において、
神聖なものは
「見るもの」ではなく、
感じ取られるものでした。
何もないその場に立つとき、
人は不思議と、
そこから離れがたくなります。
理由を探す前に、
身体がすでに、
その奥へと引き寄せられているのです。
それは、
その何もない場が、
私たちの本性と
深く響き合っているからかもしれません。
役割も、
名前も、
思考もほどけた先に、
ただ在るという感覚が残る。
奥とは、
どこか遠くにある場所ではなく、
あらゆるものを離したその先で、
すでに在り続けているところなのです。
こうした奥行きを、
風土と空間のなかに感じさせる場所が、
越後の山あいに、静かに在りました。
-300x200.jpg)
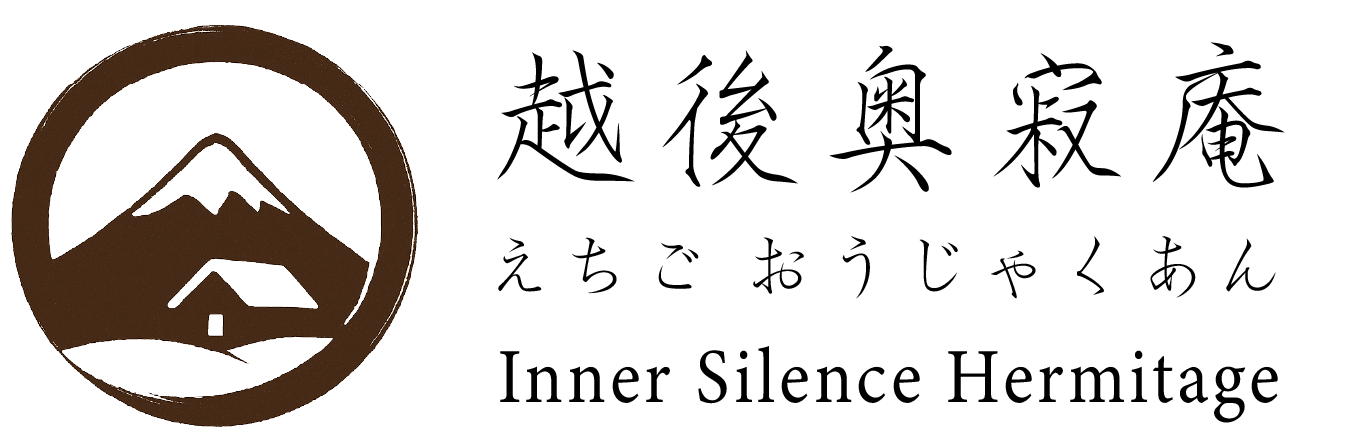
.jpg)
.png)